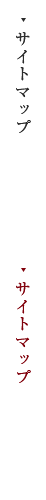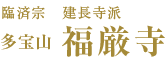ホーム > 一行三昧~足利ZEN~ > 坐禅会 > 達磨忌 10月 坐禅会 1
2025.10.05
達磨忌 10月 坐禅会 1
本日は10月最初の坐禅会でした。
早朝6時からお二人ご参加くださり、一時間半ゆったりと坐禅をして頂きました。
また本日10月5日は、禅宗の初祖達磨大師のご命日で「達磨忌(だるまき)」でした。
例年でしたら朝課にて達磨大師への読経とご回向を申し上げる法要をしております。
大本山建長寺など大寺院では多くの僧侶が集まってご法要を行います。
達磨大師の記録は不明な点が多く達磨大師がいったい何者で、いつ中国へ来たのかを正確に知ることはできません。
ある資料では、彼をペルシア(波斯)の僧であり、紀元480年に中国に来て、536年に亡くなったとあります。
また、『続高僧伝』の記録では、
達磨大師は西暦527年に中国南方の広州に到着して
やがて梁の武帝に招かれて都・南京へ赴いたとされています。
達磨大師の教えとして伝わっているものに「二入四行論」があります。
二入とは「理入」と「行入」であり、
「理入」とは、
教理によって道に入ることで、
生あるものは皆、共通の真性を有していると信じるが、
それは外物にさえぎられて発揮されていないだけなのです。
ゆえに、われわれは偽を捨て真に帰し、心を壁観に専らにして、
物我倶忘、凡聖等一の境地に到るべきであると説きます。
そうしてはじめて寂然無為にして道と相合することができるのです。
そして「行入」には四つがあります。
① 報怨行(ほうえんぎょう):
道を求めるときにもし苦難に遭うならば、
それは前世の業によるものであると考えるべきである。
今は悪を作らずとも、なお過去の報いを受けねばならぬ。
この理を悟れば、天を怨まず人を責めず、苦に逢っても憂えず、
怨みを転じて道に入ることができる。
② 随縁行(ずいえんぎょう):
世界には本来「我」はなく、
一切の苦楽は外縁によって生じる。
栄辱や禍福も前世の業の結果である。
いま現れているとしても、縁が尽きればまた無に帰する。
ゆえに、得ても喜ばず、失っても憂えず、
すべては縁に随って行うのである。(栄誉や屈辱に一喜一憂せず、どんな状況でも道と共に静かに生きること)
③ 無所求行(むしょぐぎょう):
世の人はしばしば迷い、貪り求めて飽くことがない。
しかし修道の人はそうではない。
彼らは心を無為に置き、天に順い命に安んずる。
この世の生活は苦海にほかならず、
まるで熱い鍋の上の蟻のように安らぐところがないことを深く知っている。
まさに「求むることあれば皆苦なり、求むることなければすなわち楽なり」と言うとおりである。
④ 称法行(しょうほうぎょう):
仏法とは純粋なる至理である。
この至理は光明清浄にして、けがれず、分別もない。
経に曰く、
「法に衆生なし。衆生の垢を離れるが故に。
法に我なし。我の垢を離れるが故に。」
智慧ある者はこの道理を悟り、
一切を道に随って行うべきである。
これらが達磨大師の「二入四行論」の教えでした。
日本ではユニークな姿になった縁起達磨が有名ですが、具体的な教えをも学び実践することも大切なことです。